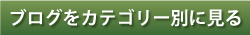▼その他バックナンバー
2025-04-25
貿易と平和
2025-04-21
西洋絵画と中国伝統絵画における視点と視線
2025-04-20
治国の先人の知恵
2025-04-17
ファーウェイ、三進法コンピューティングの新特許を登録
2025-04-11
第400回「舞劇『朱鷺』-Toki-」
2025-04-09
2025‐26年度 新米山記念奨学生 歓迎懇親会
2025-04-07
中国、昨年の平均寿命を発表
2025-03-21
和製英語(Japanese English)と中式英語(Chinglish)
2025-03-13
第四回チャイナフェスティバル札幌2025
2025-03-12
北海道開拓の歴史を学び、未来を考える
2025-03-10
晴れ男
2025-03-08
交流と感謝
2025-03-05
観梅(かんばい)の裏話
2025-03-04
「鉄打」の意味
2025-03-03
親子旅
過去ブログはこちらから
観梅(かんばい)の裏話
カテゴリー その他
梅は中国原産の花木で、2000年前に書かれた中国最古の薬物学書『神農本草経』には、すでに梅の効用が記されています。
日本に梅が伝来したのは3世紀末頃とされ、百済(くだら)の帰化人・王仁(わに)がもたらしたとする説や、欽明天皇(531年即位)の大和時代に中国・呉の高僧が伝えたという説があります。
中国では、梅は強靭な精神、純潔な姿、孤高・高潔な性格を象徴し、その品格から「君子」に例えられ、人々に深く愛されてきました。また、四季を表す花の代表として「梅」「蘭」「竹」「菊」の「四君子」の一つとされ、詩にも詠まれ、古くから人気を集めています。
中国の国花は牡丹(ぼたん)ですが、中華民国時代には外敵の災難を受けたことを背景に、国花として「梅」が選ばれました。古代の文人や貴族たちにとって、春の観梅は文化的な伝統であり、「探梅」「賞梅」「贈梅」「墨梅」「梅瓶梅」といった習慣がありました。また、寿命の長い梅の木は盆栽としても親しまれ、寒い冬に咲く花として人気があります。
日本に伝わった後も、貴族たちは「探梅」「賞梅」「贈梅」などの習慣を継承し、その歴史は現代の観梅にも受け継がれています。
2024年3月1日~2日、赤塚グループの研修で三重県鈴鹿市のFFC研究栽培農園「鈴鹿の森庭園」を見学しました。昨年はちょうど梅の花が散る時期でしたが、今年はまだ蕾の状態でした。そのため、参加者は「探梅」ツアーとなり、一輪、二輪と咲いた花を見つけて写真に収めました。
担当者によると、「梅は毎日最初に咲く花が一番美しい」とのこと。確かに、見つけた一輪の梅の花は非常に美しかったです。
「鈴鹿の森庭園」では、日本の伝統を重んじ、『匠の技』で作り上げた美しい枝垂れ梅が数多く植えられています。日本中から集められた枝垂れ梅の名木は、呉服枝垂(くれはしだれ)を中心に約200本あり、日本最大級の大木もあります。
中国では、梅の木は50年経つと古木とされますが、樹齢数百年を超えるものもあり、最も古いものでは1600年もの歴史を持ちながら今も花を咲かせています。
現代では、梅の用途に応じて「花梅」と「実梅」に分類されます。実梅は果実を収穫するためのもので、ほとんどが自家結実しないため、受粉樹を含め3品種以上を植えるのが一般的です。一方、花梅は雌蕊(しずい)がなく、実がなりません。しかし、時折遺伝子変異によって実がつくこともあります。ただし、その実は種が大きく果肉が薄いため、養分を取られて翌年の開花に影響が出ることがあり、管理者は見つけ次第摘み取ります。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という諺の通り、花梅は一度咲いた枝には二度と花がつかないため、剪定が翌年の開花にとって重要です。特に枝垂れ梅の剪定には高度な技術が必要で、「鈴鹿の森庭園」のシンボルツリー「天の龍」と「地の龍」の樹齢は100年を越え、剪定できる職人は、わずか二人だけだそうです。枝垂れ梅を美しく造形するためには、数十年にわたる人の努力が欠かせません。富士山のような美しい形を維持するため、南向きの枝が伸びすぎないよう、数年に一度植え替えて幹の向きを回転させながら手入れを行っています。
梅の花の色にも興味深い話があります。白梅とアンズが交雑することで、赤い花が生まれることがあります。また、梅は挿し木しやすいため、白梅の木に赤い花が咲くこともあります。さらに、遺伝子の突然変異によって、白と赤の花が一本の木に咲く場合もあり、「鈴鹿の森庭園」には、一つの花の中で半分が白、半分が赤になる木も見られます。
このような枝垂れ梅を美しく見せるための裏話を聞くと、観梅の楽しみが一層深まりました。
日本に梅が伝来したのは3世紀末頃とされ、百済(くだら)の帰化人・王仁(わに)がもたらしたとする説や、欽明天皇(531年即位)の大和時代に中国・呉の高僧が伝えたという説があります。
中国では、梅は強靭な精神、純潔な姿、孤高・高潔な性格を象徴し、その品格から「君子」に例えられ、人々に深く愛されてきました。また、四季を表す花の代表として「梅」「蘭」「竹」「菊」の「四君子」の一つとされ、詩にも詠まれ、古くから人気を集めています。
中国の国花は牡丹(ぼたん)ですが、中華民国時代には外敵の災難を受けたことを背景に、国花として「梅」が選ばれました。古代の文人や貴族たちにとって、春の観梅は文化的な伝統であり、「探梅」「賞梅」「贈梅」「墨梅」「梅瓶梅」といった習慣がありました。また、寿命の長い梅の木は盆栽としても親しまれ、寒い冬に咲く花として人気があります。
日本に伝わった後も、貴族たちは「探梅」「賞梅」「贈梅」などの習慣を継承し、その歴史は現代の観梅にも受け継がれています。
2024年3月1日~2日、赤塚グループの研修で三重県鈴鹿市のFFC研究栽培農園「鈴鹿の森庭園」を見学しました。昨年はちょうど梅の花が散る時期でしたが、今年はまだ蕾の状態でした。そのため、参加者は「探梅」ツアーとなり、一輪、二輪と咲いた花を見つけて写真に収めました。
担当者によると、「梅は毎日最初に咲く花が一番美しい」とのこと。確かに、見つけた一輪の梅の花は非常に美しかったです。
「鈴鹿の森庭園」では、日本の伝統を重んじ、『匠の技』で作り上げた美しい枝垂れ梅が数多く植えられています。日本中から集められた枝垂れ梅の名木は、呉服枝垂(くれはしだれ)を中心に約200本あり、日本最大級の大木もあります。
中国では、梅の木は50年経つと古木とされますが、樹齢数百年を超えるものもあり、最も古いものでは1600年もの歴史を持ちながら今も花を咲かせています。
現代では、梅の用途に応じて「花梅」と「実梅」に分類されます。実梅は果実を収穫するためのもので、ほとんどが自家結実しないため、受粉樹を含め3品種以上を植えるのが一般的です。一方、花梅は雌蕊(しずい)がなく、実がなりません。しかし、時折遺伝子変異によって実がつくこともあります。ただし、その実は種が大きく果肉が薄いため、養分を取られて翌年の開花に影響が出ることがあり、管理者は見つけ次第摘み取ります。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という諺の通り、花梅は一度咲いた枝には二度と花がつかないため、剪定が翌年の開花にとって重要です。特に枝垂れ梅の剪定には高度な技術が必要で、「鈴鹿の森庭園」のシンボルツリー「天の龍」と「地の龍」の樹齢は100年を越え、剪定できる職人は、わずか二人だけだそうです。枝垂れ梅を美しく造形するためには、数十年にわたる人の努力が欠かせません。富士山のような美しい形を維持するため、南向きの枝が伸びすぎないよう、数年に一度植え替えて幹の向きを回転させながら手入れを行っています。
梅の花の色にも興味深い話があります。白梅とアンズが交雑することで、赤い花が生まれることがあります。また、梅は挿し木しやすいため、白梅の木に赤い花が咲くこともあります。さらに、遺伝子の突然変異によって、白と赤の花が一本の木に咲く場合もあり、「鈴鹿の森庭園」には、一つの花の中で半分が白、半分が赤になる木も見られます。
このような枝垂れ梅を美しく見せるための裏話を聞くと、観梅の楽しみが一層深まりました。

2025-03-05