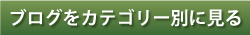▼その他バックナンバー
2026-01-07
北海道の除雪の楽しみ
2025-12-08
開拓と継承
2025-12-07
第12回 北海道中国会 総会&懇親会
2025-11-03
中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功
2025-11-01
東西文化の相違と社会形成
2025-10-20
理想の人生の模範
2025-10-15
故郷への愛
2025-10-14
黄金の秋・収穫の10月
2025-10-08
観光ラッシュ
2025-10-07
北海道観光機構への表敬訪問
2025-10-06
自転車譲渡事業の継続
2025-10-03
中国の定年後の生活
2025-10-01
連休と経済
2025-09-27
中華人民共和国成立七十六周年祝賀レセプション
2025-09-11
診療院の自然環境
過去ブログはこちらから
医学と文学
カテゴリー その他
毎月二回札幌から旭川へ、中国医学を教えるため、JR北海道に乗ります。1時間20分(今減速で1時間25分)の乗車時間、行きは昼ごはん(愛妻弁当)後、ほとんど寝ます。理由は行くのは木曜日です。木曜日の朝は札幌市倫理法人会のモーニングセミナーがあります。役員の私は4時半起き、昼は眠いです。帰りはJR北海道の車内誌を読むことを楽しみにしています。
JR北海道車内誌の特集はもちろん読みます。一番好きな内容は小檜山博氏の連載『人生讃歌』です。小檜山博氏の人生讃歌を読んで、北海道開拓時代の風景を生で見るほど、その大変さと北海道人の人間性に惚れ、共感しました。
今年一月号の特集は『文学に集う、文学が集う』北海道立文学館の20周年と特別展『小檜山博の文学』です。中身を読んだら、『小檜山博文学を読む会』もあるほど、小檜山博氏の作品が好きな方が大勢いることが嬉しかったです。
自分は医学の世界に入り、30年が過ぎました。理科系の医学は文学とは無縁でした。当時留学に北海道大学の臨床心理学を進みたい時、臨床心理学は教育学部にあり、文科系に属します。理科系出身の私の希望は教育学部の事務方にきっぱり断わられ、理系と文系は縁のない世界と思いました。
旭川出張授業のお陰で、小檜山博氏の文章力に惹かれ、今度『小檜山博の文学』の文字を見て、妙に医学と文学が繋がることを嬉しくなりました。
最近、札幌市倫理法人会の新入会員で小檜山の苗字を見て、小檜山博氏の人生讃歌が、好きと言ったら、小檜山博は私の叔父と返事が来て、親近感が生まれました。今度叔父と会う時、ファンがいることを伝えてくださいと頼んだら、喜んで『はい』と返事があり、それも嬉しくなりました。
小檜山博:滝上町生まれの小説家、小檜山博(こひやま・はく、1937年~)は、1970年代半ばから北海道に生きる人間をテーマに小説を発表し、現代社会に問いかけてきました。初期の「出刃」(1976年北方文芸賞)、中期の「光る女」(1983年北海道新聞文学賞、泉鏡花文学賞)、そして自らのルーツを凝視した「光る大雪」(2003年木山捷平文学賞)など、いずれも多くの衝撃と感動を与えています。また、エッセイスト・コラムニストとしても活躍し、心に沁みる珠玉の作品を発表。苦境にあって決して夢を忘れず、人間への希望を求める小檜山博の文学世界の魅力を紹介します。
JR北海道車内誌の特集はもちろん読みます。一番好きな内容は小檜山博氏の連載『人生讃歌』です。小檜山博氏の人生讃歌を読んで、北海道開拓時代の風景を生で見るほど、その大変さと北海道人の人間性に惚れ、共感しました。
今年一月号の特集は『文学に集う、文学が集う』北海道立文学館の20周年と特別展『小檜山博の文学』です。中身を読んだら、『小檜山博文学を読む会』もあるほど、小檜山博氏の作品が好きな方が大勢いることが嬉しかったです。
自分は医学の世界に入り、30年が過ぎました。理科系の医学は文学とは無縁でした。当時留学に北海道大学の臨床心理学を進みたい時、臨床心理学は教育学部にあり、文科系に属します。理科系出身の私の希望は教育学部の事務方にきっぱり断わられ、理系と文系は縁のない世界と思いました。
旭川出張授業のお陰で、小檜山博氏の文章力に惹かれ、今度『小檜山博の文学』の文字を見て、妙に医学と文学が繋がることを嬉しくなりました。
最近、札幌市倫理法人会の新入会員で小檜山の苗字を見て、小檜山博氏の人生讃歌が、好きと言ったら、小檜山博は私の叔父と返事が来て、親近感が生まれました。今度叔父と会う時、ファンがいることを伝えてくださいと頼んだら、喜んで『はい』と返事があり、それも嬉しくなりました。
小檜山博:滝上町生まれの小説家、小檜山博(こひやま・はく、1937年~)は、1970年代半ばから北海道に生きる人間をテーマに小説を発表し、現代社会に問いかけてきました。初期の「出刃」(1976年北方文芸賞)、中期の「光る女」(1983年北海道新聞文学賞、泉鏡花文学賞)、そして自らのルーツを凝視した「光る大雪」(2003年木山捷平文学賞)など、いずれも多くの衝撃と感動を与えています。また、エッセイスト・コラムニストとしても活躍し、心に沁みる珠玉の作品を発表。苦境にあって決して夢を忘れず、人間への希望を求める小檜山博の文学世界の魅力を紹介します。

2015-02-02