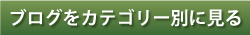▼生活の知恵バックナンバー
2026-02-02
ニュース「米国のがん死亡率は着実に減少している」について
2026-01-18
古代中国人の法則は、どのようにして生まれたのか
2026-01-14
中華料理の美味しさの秘訣
2026-01-10
テック界の巨人たちが予測するAIの未来と医療
2026-01-08
AIで何ができるの?仕事に使えるの?
2026-01-02
最強の心理暗示 ― 哲学的宣言 ―
2026-01-01
新年賀正
2025-12-31
あっという間の年末、来年の運勢について
2025-10-11
中国文化に見る“進数”の知恵
2025-09-10
濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ
2025-09-08
爪のケア
2025-09-06
札幌市倫理法人会 キックオフ会と快気祝い
2025-08-25
冷えと下痢
2025-08-24
電気自動車体験
2025-08-12
早起きは三文の徳(得)
過去ブログはこちらから
学習の本意を理解できましたか?
カテゴリー 生活の知恵
論語の教えは、「子曰。学而時習之。不亦悦乎。」(「学び、時にそれを習う。これを喜ばざるありや。」)から始まります。この言葉から、「学習」という言葉が生まれ、学習の本質を理解するには、論語の原文を勉強する必要があります。
「学」は動詞であり、学ぶことを指します。学ぶ場所は学校であり、学ぶ子供は学童、学ぶ先輩は学長などと言います。学ぶことは知識を得ることです。
「習」は実践や復習、予習、実習などを意味する動詞です。
現代の学習は授業を受けることに留まっており、本来の学習の意味を半分しか満たしていません。真の学習とは、授業を受けた後に実践することです。知識を応用することです。
現代社会は知識が溢れており、知識を持つことだけが重要ではなく、それを応用し知恵へと昇華させることが肝要です。知識から知恵へと昇華するためには、実践を繰り返すことが不可欠です。実践を通じて能力を発揮し、技術を磨き、一人前になるのです。
知識から知恵へと昇華するプロセスは文化と呼ばれます。文は文明の始まりであり、化は変化の過程を指します。教育の目的は教化であり、人を教え導くことです。
食べ物が身体にとって重要なのと同様に、学習は大脳にとって重要です。学習し実践しなければ、知識は消化されずエネルギーになりません。
「習い」は慣れることを指し、それが習慣となります。中国の諺に「習以為常」(習い性となる)があり、繰り返し行うことで不慣れなことでも慣れることができます。温故知新も同様であり、学習は知識から知恵への過程です。これを実現できれば、楽しいことです。
「学」は動詞であり、学ぶことを指します。学ぶ場所は学校であり、学ぶ子供は学童、学ぶ先輩は学長などと言います。学ぶことは知識を得ることです。
「習」は実践や復習、予習、実習などを意味する動詞です。
現代の学習は授業を受けることに留まっており、本来の学習の意味を半分しか満たしていません。真の学習とは、授業を受けた後に実践することです。知識を応用することです。
現代社会は知識が溢れており、知識を持つことだけが重要ではなく、それを応用し知恵へと昇華させることが肝要です。知識から知恵へと昇華するためには、実践を繰り返すことが不可欠です。実践を通じて能力を発揮し、技術を磨き、一人前になるのです。
知識から知恵へと昇華するプロセスは文化と呼ばれます。文は文明の始まりであり、化は変化の過程を指します。教育の目的は教化であり、人を教え導くことです。
食べ物が身体にとって重要なのと同様に、学習は大脳にとって重要です。学習し実践しなければ、知識は消化されずエネルギーになりません。
「習い」は慣れることを指し、それが習慣となります。中国の諺に「習以為常」(習い性となる)があり、繰り返し行うことで不慣れなことでも慣れることができます。温故知新も同様であり、学習は知識から知恵への過程です。これを実現できれば、楽しいことです。
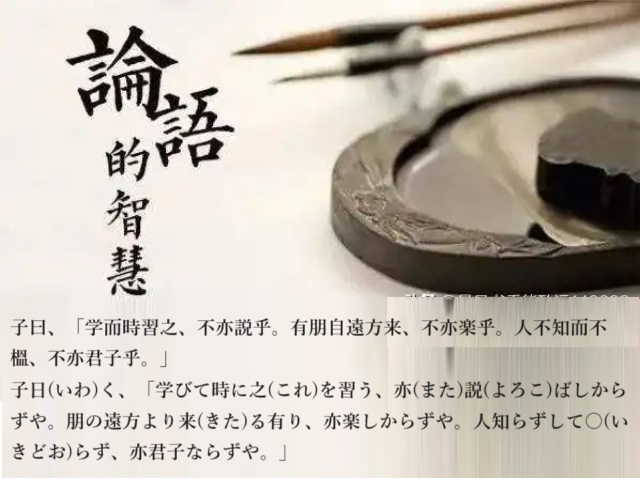
2024-04-02