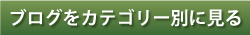▼生活の知恵バックナンバー
2026-01-18
古代中国人の法則は、どのようにして生まれたのか
2026-01-14
中華料理の美味しさの秘訣
2026-01-10
テック界の巨人たちが予測するAIの未来と医療
2026-01-08
AIで何ができるの?仕事に使えるの?
2026-01-02
最強の心理暗示 ― 哲学的宣言 ―
2026-01-01
新年賀正
2025-12-31
あっという間の年末、来年の運勢について
2025-10-11
中国文化に見る“進数”の知恵
2025-09-10
濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ
2025-09-08
爪のケア
2025-09-06
札幌市倫理法人会 キックオフ会と快気祝い
2025-08-25
冷えと下痢
2025-08-24
電気自動車体験
2025-08-12
早起きは三文の徳(得)
2025-08-12
故郷の味
過去ブログはこちらから
冬至の養生陰陽
カテゴリー 生活の知恵
11月22日、冬至、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日(南半球では逆転する)です。これから昼は長くなり、陰極に至る、一陽が生まれ成長が始まります。中国の旧暦で、一番大事にする節気です。陽気が始まるときに、もっとも重要な時期で、種まきと同じ、タイミングをつかみ、身体の陽気が生まれ育ち、持病を持っている方も、回復のポイントでしょう。難病奇病の方、冬至を過ぎたら、治って来る傾向が臨床医の実感です。
日本ではかぼちゃを食べ、柚湯をする習慣で、中国では、餃子やワンタンを食べる習慣があります。冬の陽気は「蔵」(貯蔵する)という漢字を使います。外出するときに、三首(肩首、手首、足首)の防寒措置、大量の汗(激しい運動・キツイ労働など)を出さないこと、暴飲暴食(陽気を消耗する)を避けること、感情の激しくすることを避け、背中に太陽を浴びる、背中かっさ、お灸などの養生をする、羊肉を餃子の餡にして食べるなど、長芋や栗など食材を積極的に取り入れるほど、陽気と人気を補います。
冬至(とうじ、英: winter solstice)は、二十四節気の第22。天文・平気法・周正などの節切りでは第1となり、暦法上は冬至で1年間の干支が切り替わる[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。夏正では第22となる。北半球ではこの日が一年で最も日の出から日没までの時間が短い。旧暦11月に存在するが、周代などの王朝では冬至の存在する子月を1月とし、子月後半の最初である冬至を1年の始まりとし、冬至前日を大晦日としていた(子後半で始まり、子前半で終わる)。(Wikipediaより)
日本ではかぼちゃを食べ、柚湯をする習慣で、中国では、餃子やワンタンを食べる習慣があります。冬の陽気は「蔵」(貯蔵する)という漢字を使います。外出するときに、三首(肩首、手首、足首)の防寒措置、大量の汗(激しい運動・キツイ労働など)を出さないこと、暴飲暴食(陽気を消耗する)を避けること、感情の激しくすることを避け、背中に太陽を浴びる、背中かっさ、お灸などの養生をする、羊肉を餃子の餡にして食べるなど、長芋や栗など食材を積極的に取り入れるほど、陽気と人気を補います。
冬至(とうじ、英: winter solstice)は、二十四節気の第22。天文・平気法・周正などの節切りでは第1となり、暦法上は冬至で1年間の干支が切り替わる[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。夏正では第22となる。北半球ではこの日が一年で最も日の出から日没までの時間が短い。旧暦11月に存在するが、周代などの王朝では冬至の存在する子月を1月とし、子月後半の最初である冬至を1年の始まりとし、冬至前日を大晦日としていた(子後半で始まり、子前半で終わる)。(Wikipediaより)
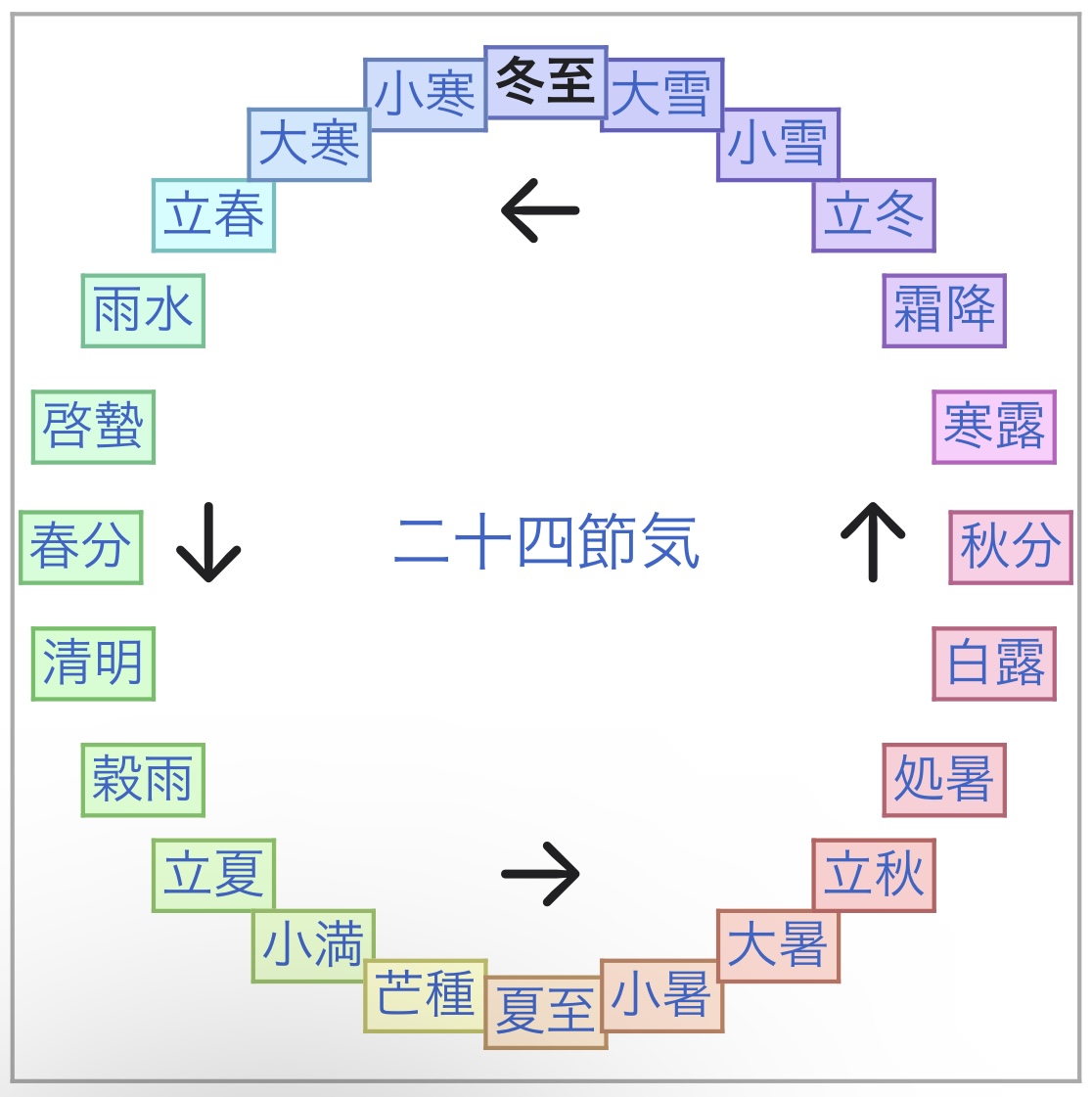
2022-12-23