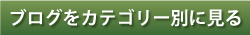▼その他バックナンバー
2025-12-08
開拓と継承
2025-12-07
第12回 北海道中国会 総会&懇親会
2025-11-03
中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功
2025-11-01
東西文化の相違と社会形成
2025-10-20
理想の人生の模範
2025-10-15
故郷への愛
2025-10-14
黄金の秋・収穫の10月
2025-10-08
観光ラッシュ
2025-10-07
北海道観光機構への表敬訪問
2025-10-06
自転車譲渡事業の継続
2025-10-03
中国の定年後の生活
2025-10-01
連休と経済
2025-09-27
中華人民共和国成立七十六周年祝賀レセプション
2025-09-11
診療院の自然環境
2025-09-05
国別平均IQスコア
過去ブログはこちらから
『私の故郷「梁荘」そして中国』
カテゴリー その他
7月19日、札幌大学サテライトキャンパスで、第26回孔子学院講演会(講師:梁鴻氏)に参加し、中国青年政治学院中文学院教授の梁鴻氏をお迎えして、梁氏の著書(『中国における梁荘』と『梁荘を出る』)の内容に沿い現代中国農村の現状と課題に関するご講演を聴講しました。
1970年代出身の梁教授は梁荘生まれ、20歳まで生活をしています。2008-9年、大学の教授として、ふるさとに五ヶ月考察し、親戚や農村の人々をインタービューし、文学の手法で、中国現代化の軌道に農村はどんな運命をたどっているのでしょうか?中国の農村をそのままで映し出して二冊本を出版しました。
講演中、インタービューした人物を中心に変革に伴う陣痛を掘り下げながら、梁荘の人々の運命、年寄り、婦人や児童たちの物語を記述していき梁荘の農村生活を再現しました。『梁荘を出る』は中国の各都市に出稼ぎに出て行きました。
梁荘の人々の物語は梁荘からの出稼ぎ農民たち(つまり「農民工」)は、どんな都市でどのように仕事、生活、居住しているのでしょうか、そして彼らの愛情、彼らの土地からの移動などを通して、故郷の梁荘、そして出稼ぎの場としての都会をどのように認識し考えているのかを探り、中国現代の「農民工」と都市との関係を考察しました。
二つの「梁荘」の自然環境、文化構造、倫理構造や道徳構造を考察し、故郷梁荘はこの半世紀でたどってきた歴史的な運命と精神状況を描き出したい内容、今度の講演では以上のように「梁荘」の人々の物語と運命を通して、中国現代農村の現状と課題を提起し考えるものになりました。
講演中、講師の五番目のお婆さんの孫の水死(11歳)から、出稼ぎ息子夫婦との関係、その後息子をなくした叔父夫婦は次男を生み、子供に生活に向かない環境で一緒に生活する場面を語り、中国発展途中の生々しい感を伝えました。
大都市(上海)に生まれた自分、梁教授を語った現代中国の農村、なんとなく聞いた、見ました内容と合わせ、とても懐かしいです。経済発展から、社会変革し、最後に影響されるのは国民です。もともと農業大国の中国、変化に多きのは農民でしょう。農民たちは生存の空間を探すため、大都市に「出稼ぎ」、「農民工」になりました。しかし戸籍の問題で、経済、教育、医療などの差別が生じます。講演を通じて、それは全地球にも通用する各階級、民俗、貧富間の人間関係の問題です。本来の伝統、古い村、どう存続するなど事も課題に提起し、とても考え深い、面白い講演会です。
北海道中国会は代表田義之はじめ、陶恵栄委員長、滝沢先生、山下副委員長、菊地さんと花島さんを参加しました。最後に講師と写真を撮り、楽しい講演会でした。
1970年代出身の梁教授は梁荘生まれ、20歳まで生活をしています。2008-9年、大学の教授として、ふるさとに五ヶ月考察し、親戚や農村の人々をインタービューし、文学の手法で、中国現代化の軌道に農村はどんな運命をたどっているのでしょうか?中国の農村をそのままで映し出して二冊本を出版しました。
講演中、インタービューした人物を中心に変革に伴う陣痛を掘り下げながら、梁荘の人々の運命、年寄り、婦人や児童たちの物語を記述していき梁荘の農村生活を再現しました。『梁荘を出る』は中国の各都市に出稼ぎに出て行きました。
梁荘の人々の物語は梁荘からの出稼ぎ農民たち(つまり「農民工」)は、どんな都市でどのように仕事、生活、居住しているのでしょうか、そして彼らの愛情、彼らの土地からの移動などを通して、故郷の梁荘、そして出稼ぎの場としての都会をどのように認識し考えているのかを探り、中国現代の「農民工」と都市との関係を考察しました。
二つの「梁荘」の自然環境、文化構造、倫理構造や道徳構造を考察し、故郷梁荘はこの半世紀でたどってきた歴史的な運命と精神状況を描き出したい内容、今度の講演では以上のように「梁荘」の人々の物語と運命を通して、中国現代農村の現状と課題を提起し考えるものになりました。
講演中、講師の五番目のお婆さんの孫の水死(11歳)から、出稼ぎ息子夫婦との関係、その後息子をなくした叔父夫婦は次男を生み、子供に生活に向かない環境で一緒に生活する場面を語り、中国発展途中の生々しい感を伝えました。
大都市(上海)に生まれた自分、梁教授を語った現代中国の農村、なんとなく聞いた、見ました内容と合わせ、とても懐かしいです。経済発展から、社会変革し、最後に影響されるのは国民です。もともと農業大国の中国、変化に多きのは農民でしょう。農民たちは生存の空間を探すため、大都市に「出稼ぎ」、「農民工」になりました。しかし戸籍の問題で、経済、教育、医療などの差別が生じます。講演を通じて、それは全地球にも通用する各階級、民俗、貧富間の人間関係の問題です。本来の伝統、古い村、どう存続するなど事も課題に提起し、とても考え深い、面白い講演会です。
北海道中国会は代表田義之はじめ、陶恵栄委員長、滝沢先生、山下副委員長、菊地さんと花島さんを参加しました。最後に講師と写真を撮り、楽しい講演会でした。

2015-07-20